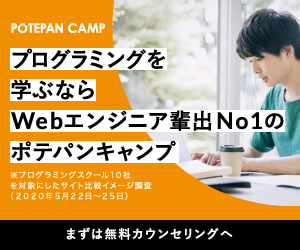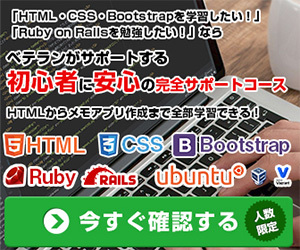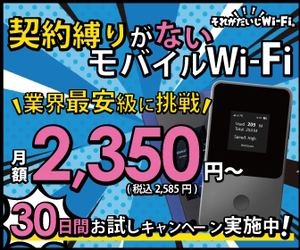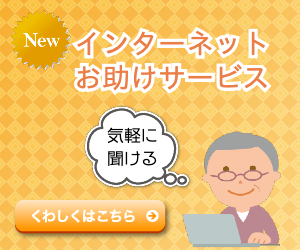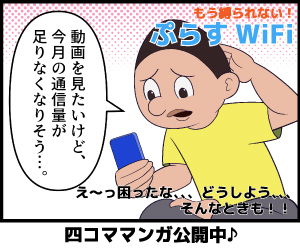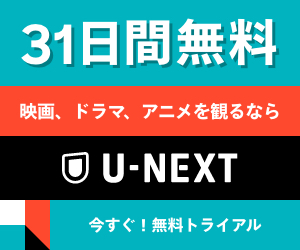- 1. boot ディスクからの起動
- 2. 国の選択
- 3. キーマップの設定
- 4. sysinstallの起動
- 5. パーティションの設定
- 6. ディスクラベルの設定
- 7. 配布ファイルの選択
- 8. インストールメディアの選択
- 9. インストール
- 10. システム環境設定
- 11. タイムゾーンの設定
- 12. rootパスワードの設定
- 13. OSインストール終了
1. boot ディスクからの起動
以前は、フロッピーからの起動についても記述しておりましたが、現在はフロッピーレスなマシンも多々ありますので、「CD-R」からの起動から話を進めていきます。
「ISO」イメージで作成した「CD」は、「boot」可能ディスクになっています。
「BIOS」で「CD」 ドライブからの起動が有効になっていることを確認したら、「CD」ドライブに「boot」ディスクを挿入して、電源を投入します。
しばらくすると、以下の画面が表示されます。
これは 「boot」モードの選択画面です。
「default」で進めますので Enter キーを押下します。
2. 国の選択
初回の起動時は「Country Selection」が表示されます。
デフォルトで「United States」が選択されています。
日本語をベースとするのであれば「Japan」を選択します。
3. キーマップの設定
キーマップを設定します。
「Country Selection」で「Japan」を選択していれば「Japanese 106」が選択されているはずです。日本語 JIS のキーボードを使用しているのであれば、そのまま進みます。
4. sysinstall の起動
「sysinstall Main Menu」が表示されます。
「Custom」を選択します。
5. パーティションの設定
ディスクパーティションの設定を行います。「Partition」を選択します。
以下のような画面が表示されます。
もし、今までにディスクをWindowsなどに使用していた場合、usedになっている個所があります。
ディスクを全部 FreeBSD で使用するのであれば、既存のスライスがある行を反転表示させ、[D]キーを押下します。ディスク全体が「unused」になるまで繰り返します。
ディスクに反転行カーソルを合わせた状態で、[C]キーを押下します。
割り当てるサイズが示されますが、ここではディスクの全領域を FreeBSD に使用しますので、そのまま [Enter]キーを押下します(ディスクをいくつかのパーティションに分ける場合は、数字を入力してサイズを指定します。サイズを指定する場合、数字の後に [M] をつけることで MB 単位のサイズを [G] をつけることで GB 単位のサイズを指定することが可能です)。
生成するパーティションのタイプを聞いてきます。
FreeBSD のパーティションタイプは 165 であり、デフォルトでその値になっていますので、そのまま [Enter] キーを押します。
ディスクの先頭に unused の領域が残りますがこれは気にしないで下さい。
この領域には起動管理プログラム・パーティションテーブルというものがはいります。
誤った容量を設定してしまった場合は、一旦パーティションを削除し、サイド正しい容量で設定しなおしてください。
容量設定後この画面を抜けるために、[Q] を押下します。
boot マネージャーのインストールメニューが表示されます。
デフォルトでりboot マネージャーをインストールする設定が選択されていますので、そのまま [Enter]キーを押下します。
6. ディスクラベルの設定
カスタムメニューで「Label」を選択します。以下のようなメニューが表示されます。
ここで、ディスクラベルの設定を行います。ディスクラベルの分け方にはいろいろありますが、ここでは基本的に以下の4つのディスクラベルを作成します。
| / | ルートラベル |
| /swap | スワップ用ラベル |
| /var | ログファイル用ラベル |
| /usr | ユーザ用ラベル |
「/」ルートラベルには、最低 64MB の領域が必要です。ディスクの容量に合わせて、ディスクの 10% くらいまで割り当ててもいいかと思います。
「/swap」スワップ用ラベルには、実装メモリの 2 倍以上を目安に割り当ててください。それ以下だと、システムがロックしてしまうことがあるようです。
残りの領域を「/var」と「/usr」で半々に分けてください。
以上はあくまで目安であり、使い方によってはもっと細かくラベルを分けたりサイズの比率を調整することが必要になります。
ルート用ラベル
仮に 10GB のディスクが実装されているとして、「/]に 1024MB、「/swap」に 512MB、「/var」に 4352MB、「/usr」に 4352MB割り当てるとします。
前項で、スライス全体を FreeBSD に割り当てていますので、ディスクの領域は 1 つ表示されていると思います。
ルート用スライスが反転表示されている状態で [C] を押下します。
容量選択画面で [1024M] と入力して [Enter] を押します。
確保した領域を何に使うか聞いてきますのでここでは「FS file system」を選択します。
ラベルのマウント位置を聞いてきますのでルート用として[/]と入力して[Enter]を押します。
これでルート用ラベルは作成できました。
スワップ用ラベル
選択ディスクを下の方に持っていきます。下のディスクが反転表示になっている状態で、[C]を押下します。
容量選択画面で [512M] と入力して [Enter] を押します。
確保した領域を何に使うか聞いてきたら「Swap Swap partition」を選択します。
ログファイル用ラベル
下のディスク反転表示のまま、[C]を押下します。
容量選択画面で [4352M] と入力して[Enter]を押します。
確保した領域を何に使うか聞いてきたら「FS file system」を選択します。
マウント位置を聞いてきたらログファイル用として [/var] と入力して [Enter] を押します。
ユーザファイル用ラベル
下のディスク反転表示のまま [C] を押下します。
容量選択画面には残りのサイズがでてきます。残りの領域はすべてユーザファイル用に割り当てるのでそのまま [Enter] を押します。
確保した領域を何に使うか聞いてきたら「FS file system」を選択します。
マウント位置を聞いてきたらログファイル用として [/usr] と入力して [Enter] を押します。
ディスク容量に余裕のある場合は、この他に、
ログインユーザ用ラベル
という領域を割り当ててもよいでしょう。ディスク容量に余裕があり、多くのログインユーザを登録する予定であれば、「/home」配下を別領域として割り当てるわけです。
上記の方法には、異論のある方も多いかと思いますし、ディスクをどのように切り分けるか考えるのが面倒だという人もいると思います。そんなとき、お手軽なのは、[A] 押下です。自動的に、デフォルトの設定をしてくれます。
これでラベルの設定が完了しましたので [Q] を押下して「FreeBSD Disklabel Editor」を抜けます。
7. 配布ファイルの選択
カスタムメニューで「Distributions」を選択します。以下のようなメニューが表示されます。
今回は、インターネットサーバを構築するので「Developer」もしくは「Kern-Developer(カーネル開発者)」を選択します。
今度は、以下の確認メニューが表示されます。
これは、何語のドキュメントをインストールするかを選択するもので、必要なドキュメントの言語を選択します。
次は、以下の確認メニューが表示されます。
これは「FreeBSD の ports コレクションをインストールしますか?」という意味です。
ports については後述していますが、必要なものですのでこのまま [Enetr] キーを押下します。
配布ファイル選択メニューに戻るので、「Exit(終了)」を選択してカスタムメニューに戻ります。
8. インストールメディアの選択
カスタムメニューで「Media」を選択します。
インストールするメディアの選択画面「Choose installation Medeia(メディア選択メニュー)」が表示されます。
ここでは、CDROM でインストールしますので「CD/DVD」を選択します。
デフォルトで「CD/DVD」が選択されていますので、そのまま [Enter] キーを押下します。
9. インストール
ここから、ハードディスクへの実際の書き込みに入ります。
カスタムメニューで「Commit」を選択します。
ここまでの設定ではまだハードディスクには何も書き込まれていません。
ここから先へ作業をすすめるとディスクの内容が消去されてしまうので「User Confirmation Requested云々」と警告メッセージが表示されます。
「Yes」を選択して先へ進みます。
書きこみ作業は、マシンのCPUスピード、ディスクへのアクセススピード等により 10~60 分ほどかかるかと思います。
10. システム環境設定
書き込みが完了すると環境設定を行うかどうかを確認するメッセージが表示されます。
ここは「Yes」を選択して以下の環境設定を行います。
以下のような「FreeBSD Configuration Menu(FreeBSD 環境設定メニュー)」が表示されます。
- 注意 -
このインストール時でなく、通常に立ち上がっている状態で、sysinstallを終了して、コマンドプロンプトに戻った状態でキーボードからコマンドを入力しても画面に文字が表示されないことがあります。そのときは、画面に文字が表示されない状態で「stty sane」と入力してください。もとに戻るはずです。
11. タイムゾーンの設定
FreeBSD 環境設定メニューから「Time Zone(タイムゾーン)」を選択します。
以下の確認メニューが表示されます。
これは「このマシンのCMOSクロックをUTC(協定世界時)に合わせた状態で使用しますか?」という意味です。日本時間を使用しますので「No」のまま [Enter] キーを押下します。
次に「Time Zone Selecter(地域選択)」というメニューが表示されます。
「Asia」を選択します。
「Countries in Asia」という国名選択メニューが表示されます。
「Japan」を選択します。
FreeBSD3.0以前は、「Japan Time Zone」で「south Ryukyu Islands(沖縄時間)」と「most locations」の選択肢が表示されていました(笑)が、この場合は「most locations」を選択します。
FreeBSD4.0以降は、この選択肢はありません。
次は、以下の確認画面が表示されます。
「'JST'を使いますか?」という意味です。
このまま「Yes」で [Enter] キーを選択します。
設定を終了し「FreeBSD Configuration Menu」に戻ります。
12. root パスワードの設定
「FreeBSD Configuration Menu」から「Root Password」を選択します。
画面左下にパスワード入力欄が表示されるので、パスワードを入力します。
確認欄もあるのでそちらにも入力します(パスワード入力欄、確認欄ともに打ち込んだキーはエコーバックされません)。
数秒後、自動的に「FreeBSD Configuration Menu」に戻ります。
13. OSインストール終了
前節までで、OSのインストールは終了です。
「Exit」を選択しつづけて、「sysinstall Main Menu」まで戻ります。
[X]キーを押してインストールを終了します。
以下のようにフロッピーとCDROMを抜くように指示が出ますが、CDROM はリセットされるまで抜けません。
ここでは「Yes」を選択します。
処理終了のためのディスクアクセスがわずかに続いたあと、パソコンにリセットがかかります。
リセットが実行されたら「CDROM」を抜きます。
ここまでの作業にミスがなければ、とりあえず、「FreeBSD」の「OS」はインストール済みなので。
リセット後、「FreeBSD」のシステムが立ち上がってくるはずです。
上記のようにログインプロンプトが表示されれば、少なくとも「FreeBSD」は立ち上がっています。
ユーザ名「root」と「12. root パスワードの設定」で入力したパスワードを入力してください。
そうすれば、FreeBSDのrootユーザとしてログインし、以降の作業ができるようになります。
|